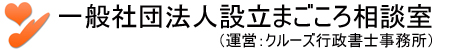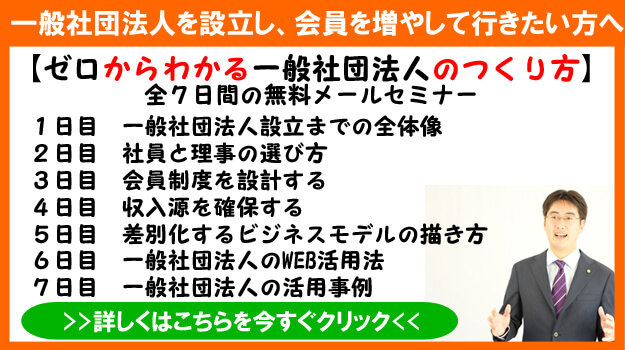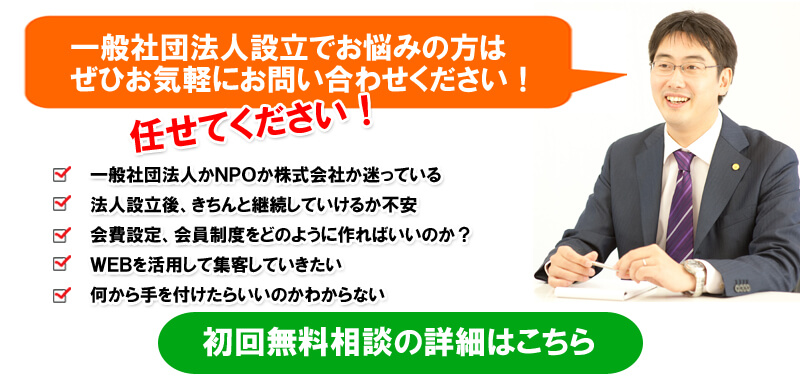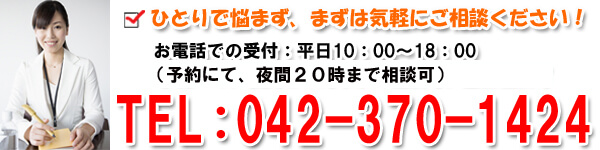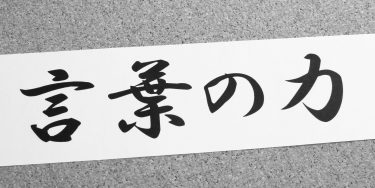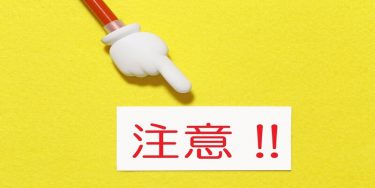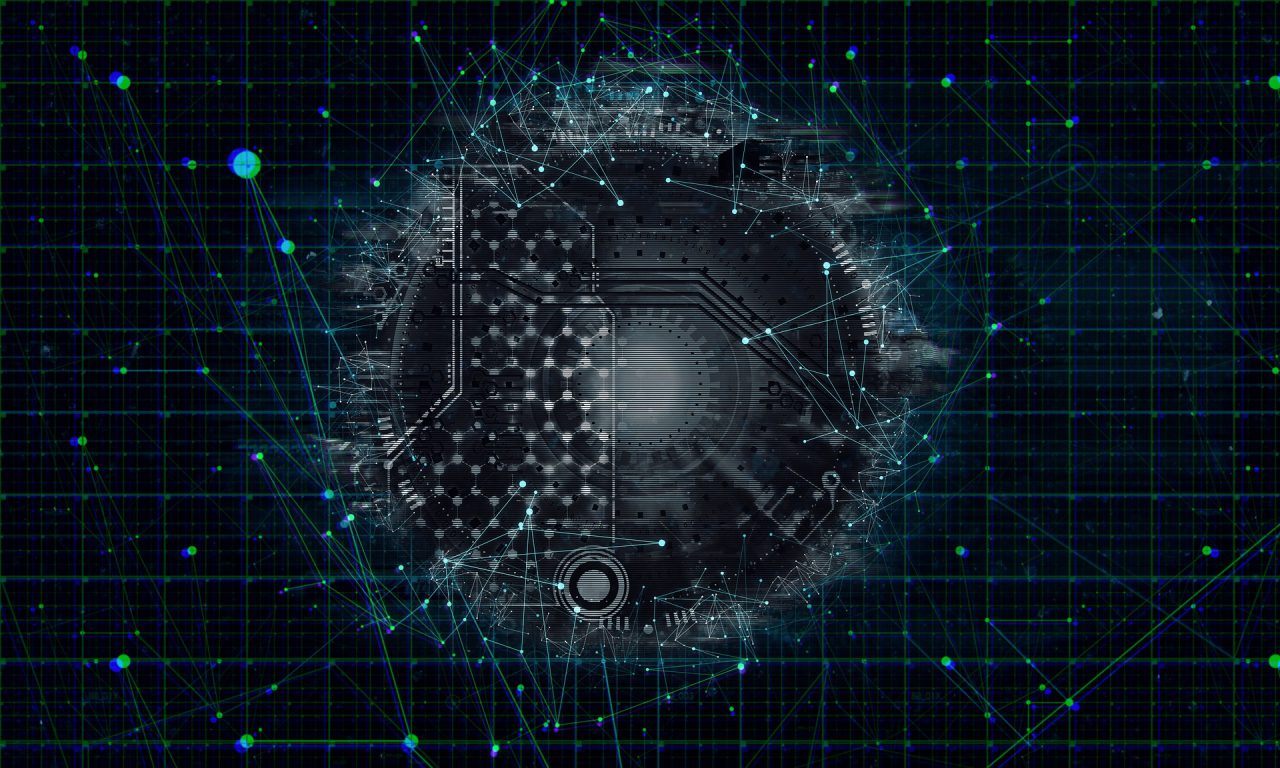一般社団法人とソーシャルビジネス
ソーシャルビジネスとは?
「ソーシャルビジネス」という言葉をご存知ですか?
簡単にいえば、社会的課題を解決することを最大の目的としたビジネスのことです。
利益を上げ続けるビジネスモデルをつくることで、社会問題の解決に継続的に関与できるメリットがあります。
「人や社会のために」というと普通の会社やNPO法人と同じような感じもしますが、解決の緊急性・難易度が高く、まだ手をつけられていない課題解決を最大の目的としているあたりが、通常のビジネスとの違いでしょうか。
ちなみに経済産業省によれば、
「環境保護、高齢者・障がい者の介護・福祉から、子育て支援、まちづくり、観光等に至るまで、多種多様な社会課題」の解決のために、「住民、NPO、企業など、
様々な主体が協力しながらビジネスの手法を活用して取り組む」ことが、ソーシャルビジネスやコミュニティビジネスであると説明されています。
一般社団法人とソーシャルビジネス
地域の課題に取り組むという意味で、コミュニティビジネスと呼ばれることもあります。
利益を最大化することが一番の目標ではなく、社会の課題を解決するための資金を稼ぐために、収益を求める、という点がソーシャルビジネスの特徴といえます。
このあたりは、一般社団法人やNPO法人の設立をお考えになる方は共感できる部分もあるのではないでしょうか。
また最近は、企業のCSR活動もずいぶん定着してきました。
CSRとは、企業の社会的責任のことです。
具体的にどういう意味かというのは、国や企業によって考え方にも差がありますが、おおむね、企業は短期的な利益を追求するだけでなく、主体的に社会に貢献する活動もする必要があるといった意味です。
単に利潤を追求するだけでなく、社会に貢献する姿勢というのが、一般の企業にも求められるようになったということです。
ボランティアとの最大の違いは、事業によって収益を上げるかどうかです。
ソーシャルビジネスの場合は、社会的課題を解決するための事業を行い、その事業を通じて直接利益を上げますが、ボランティアは事業を通して利益を上げることはせず、寄付などで資金をまかなっています。
私は、大学に入学して、子どもとキャンプ活動を行うボランティア活動とめぐり合いました。
私は最初、キャンプ活動は目的ではなく、子ども成長のための手段であると教えられました。
私たちのキャンプは8名から12名のグループを作り、グループ活動を通して人間関係や絆を深めることを一番大切な価値として考え、表面的なつながりではなく、「絆」の大切さを子どもに伝えるために活動をしていました。
子どもの成長を考え、子どものためのプログラムを作り、夏は海でのキャンプ、冬はスキーキャンプやスケート教室を行っていました。
その結果子どもの成長を感じ、笑顔を見ることが喜びとなりました。
ひとつのひとつのプログラムに思いを込めて、また先輩の方々からのいろんな教えもあり、ひとつの活動をやり終えるたびに自分が成長している事が体感でき、非常にやりがいを感じていました。
しかし1994年12月、残念ながらその団体から1995年3月をもって活動を停止すると宣言されました。
理由は赤字が続いていたからとのことでした。
こんなにやりがいがあって、子どもの成長という社会に貢献できる活動なのに、活動できない。
当時大学1年生でしたが、自分の生きがいを取られたようなショックを受けました。
この経験からも、人や社会に貢献できるのに資金がないために継続できない、という事態を防ぐために、ソーシャルビジネスというのは注目に値する事業形態だと感じています。
ボランティアだけでは生活していくことができません。
社会に貢献し人に感謝されながら、収益もきちんと上げていかないと続けることができません。
人のためにもなり、売上も確保する、ここが難しいところですが、これを達成できなければあなたの思いも実現できません。
私は常々、社会起業においてミッションや思いといった内面的なものが大切というお話をしてきました。
一般社団法人を立ち上げた後はいろいろ大変なこともあるかと思います。
すべてが順風満帆という方は少ないでしょう。
そこで踏ん張れるかどうかは、あなたの内面の想いの強さだと考えます。
・私はこの商品を広めて多くの人の役に立ちたい
・私はこのサービスを通じて社会貢献したい
・私はこの価値を伝えたい
そういうことを考え、一般社団法人を立ち上げたときの自分と向き合うことが大切だと考えています。
もちろん、ここでソーシャルビジネスが最も価値がある、と言いたいわけではありません。
ボランティアもソーシャルビジネスも、株式会社も一般社団法人も、どれも必要とされているから存在するわけで、どれかが一番いいなんてことはありません。
今回、ソーシャルビジネスという最近注目されている言葉を紹介しつつ、人に感謝されながら収益化を図ることが大切です、ということをお伝えしたかったのです。
そして、サービスや商品には自信があるけど、集客や収益に困っている、つまり継続性を維持するのに苦労している、という方の助けになりたいと考えています。