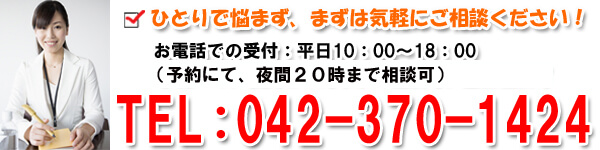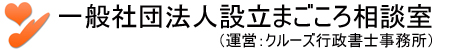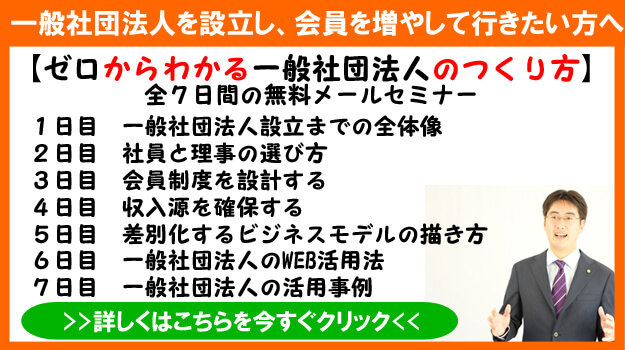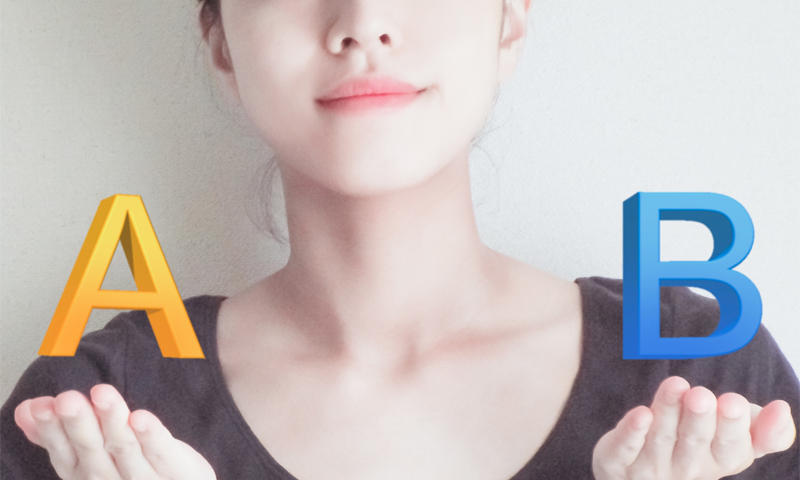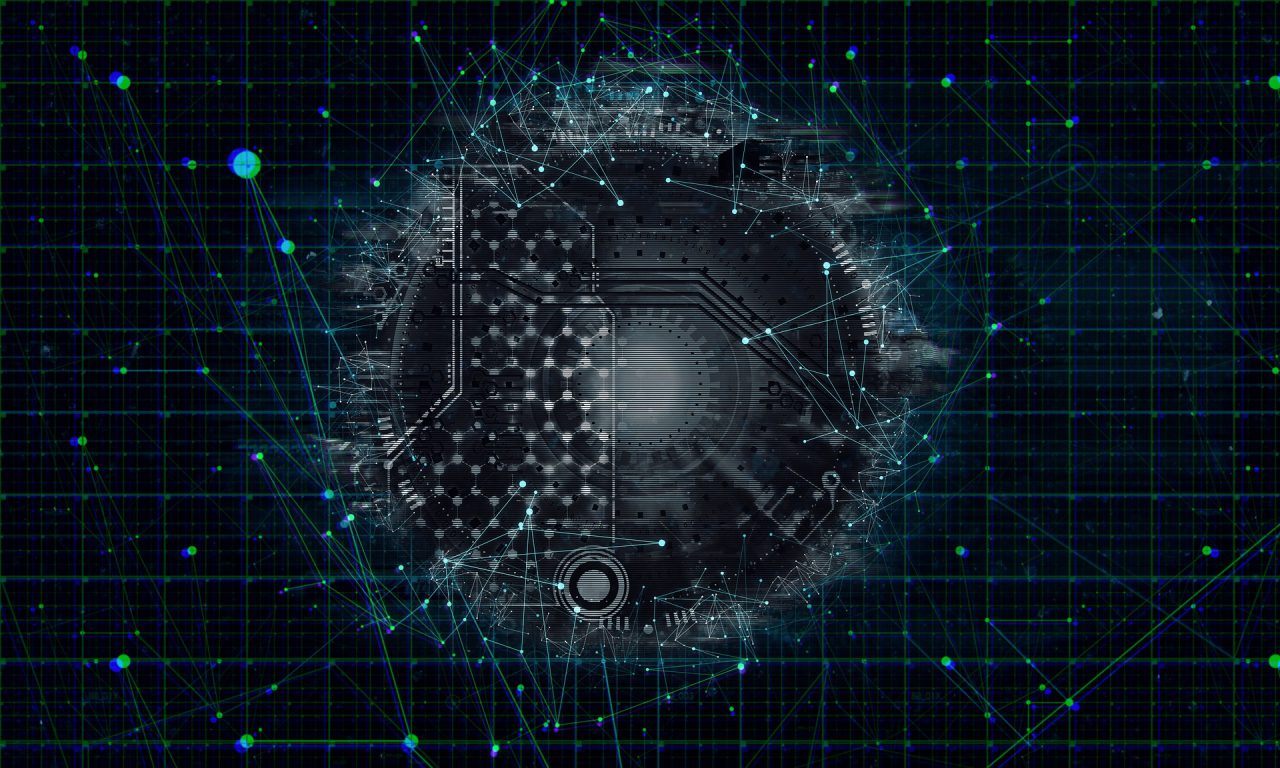1 一般社団法人と一般財団法人の違いについて
一般社団法人と一般財団法人は、名前も少し似ていて、どっちがどのようなものなのか、はっきり区別がつきにくいと思います。
まず結論から言うと、
人の集まりに対しての法人格が、一般社団法人。
人が集まって活動したり、サービスを提供したりします。
それに対して、
お金の集まりに対しての法人格が、一般財団法人。
人がお金を持って集まって、そのお金を運用した活動をしています。
です。以下で詳しく見ていきましょう。
一般社団法人と一般財団法人の違い早見表
| 一般社団法人 | 一般財団法人 | |
| 設立時の基礎財産 | 不要 | 300万円以上 |
| 設立時に必要な人数 | 最低2人 | 最低7人 |
| 定款に必要な項目数 | 7項目 | 10項目 |
2 設立時の基礎財産
一般社団法人の場合
一般社団法人は、人(一般社団法人では「社員」にあたる)による事業のために設立されるので、設立時にいくら資金がないといけない、という決まりはありません。
ここで、「社員」という言葉で誤解をされる方がいます。
一般的に「社員」というと会社の従業員をイメージされる方が多いかもしれません。
しかし、ここでいう「社員」とは、総会で議決権を有する会員のことをさします。
会社で言う「株主」の方がイメージ的には近いかもしれません。
「正会員」という呼ばれ方をすることもあります。
職員や従業員のことではありません。
一般財団法人の場合
一方、一般財団の場合、設立時に300万円以上の財産が必要です。
財産というのは、不動産と動産の両方が含まれます。
不動産の場合は、価値が300万円以上でなければいけないことになります。
そもそも一般財団法人は、
このお金や資産を、ある目的の下に運用するためにつくられる法人のため、
設立時に300万円以上集めなければならない、という少し高いハードルがあります。
集められた財産に対して法人格が与えられる、ともいえます。
3 設立費用のちがい
設立までの流れは、定款を作り公証役場で認証してもらい、法務局で登記申請をするのは、一般財団法人と一般社団法人は同じです。
<公証役場での定款認証>
認証手数料⇒5万円
定款の謄本作成代(定款の枚数によって異なる)⇒大体2千円~3千円
<法務局への登記申請>
登録免許税⇒6万円
どちらも、約11万円の費用がかかります。
一般社団法人の設立時に基本財産は必要ありませんが、設立費用は必要ですので、ご準備ください。
4 設立時に必要な人数
一般社団法人の場合
一般社団法人の場合、社員2名以上、理事1名以上いれば設立できます。
さらに、2名の社員のうち1名が理事を兼ねることができるため、実質最低2人いれば、一般社団法人を立ち上げることができるのです。
最低2人いれば起業でき、人数を集めるのにあまり苦労しなくて済む点は、一般社団法人のメリットではないでしょうか。
一般財団法人の場合
一般財団の場合、設立人1名、理事3名、評議員3名、監事1名が必要で、設立者が理事などの役職にもつけるため、最低7名必要ということになります。
一般社団の2名と比べると、必要とする人数の面では、一般財団を設立する条件が厳しいといえます。
評議員という役職は一般社団にはないものですが、財団法人の運営を監査する立場のようなものになります。
5 定款に必要な項目数
一般社団法人と一般財団法人とでは、定款に記す内容も少し違ってきます。
定款に書かなければならないこととして、以下があります。
・絶対に書かなければならない「絶対的記載事項」
・該当する決まりがあるなら記載する必要がある「相対的記載事項」
絶対的記載事項の一覧を比較してみましょう。
一般財団法人の定款に記載しなければならないこと
目的
名称
主たる事務所の所在地
設立者の氏名又は名称及び住所
設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
設立時会計監査人の選任に関する事項(会計監査人設置法人である場合)
評議員の選任及び解任の方法
公告方法
事業年度
このように、組織の構成要素(役職の名前、働き)が違うため、要求される項目が変わってきます。
6 一般社団法人と一般財団法人のちがい
言葉が似ていて違いが分かりにくい「一般社団法人」と「一般財団法人」ですが、いくつか相違点があります。
特に「基本財産」と「設立時に必要な人数」は、設立をお考えの際の重要なポイントになると思いますので、どちらがよいか検討してみてください。
一般社団法人や一般財団法人、NPO法人の設立をお考えの方は、まずは、設立事前相談にお申し込みください。