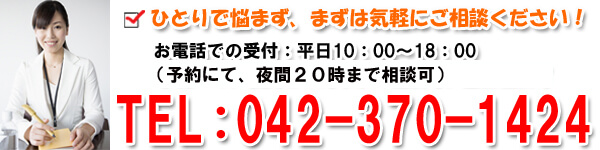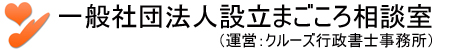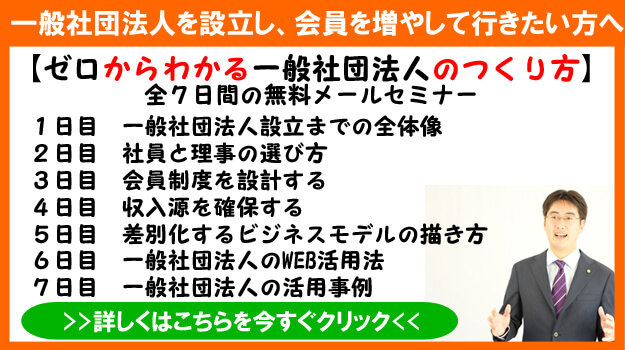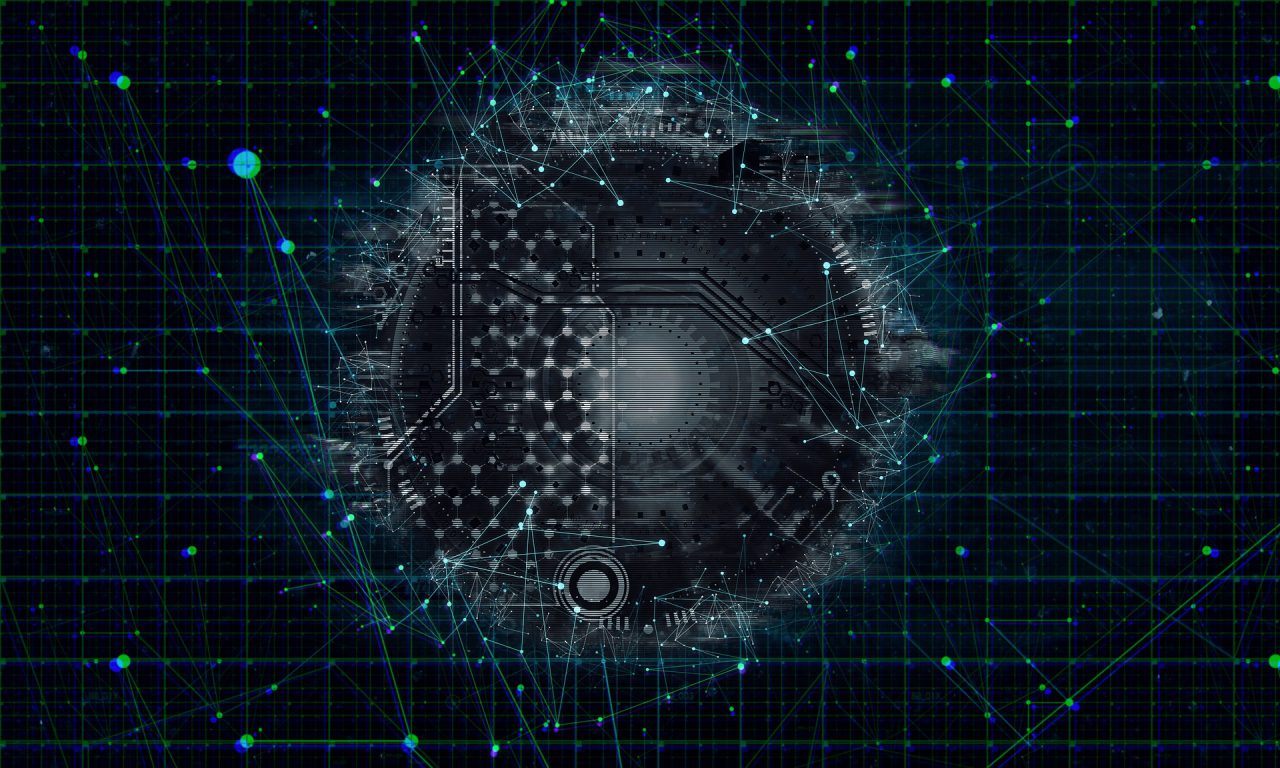一般社団法人設立のメリット・デメリット
一般社団法人とは、2008年に制定された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。
起業を考える際には、一番最初に思い浮かぶのは株式会社かもしれません。
一般社団法人は2008年にできたばかりの法人形態ですので、株式会社やNPO法人に比べればまだ馴染みが薄いと思います。
そこで、一般社団法人のご説明を兼ねて、一般社団法人を設立し事業を行うメリット・デメリットを挙げていきたいと思います。
一般社団法人設立のメリット
1.事業に制限がない
一般社団法人というやや特殊な法人形態だと、公益性の高い事業をしなければならないなど、事業内容に制限がある、というイメージがあるかもしれません。
しかし、一般社団法人の場合、事業内容に制約がありません。
株式会社と同じように利益を追求した活動を行っても問題ありません。
NPO法人の場合は、特定非営利活動促進法に定められ、「20分野の非営利活動」に活動内容が限られます。
1保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2社会教育の推進を図る活動
3まちづくりの推進を図る活動
・・・
全ては書き出しませんが、活動の内容が公益の増進に寄与するものでなければいけません。
一方、一般社団法人には活動の制約が法律上は一切ありません。
ということで、NPO法人と同じく「公益の増進に寄与する活動」も勿論行うことができますし、NPO法人では認められていない、特定の者のみが利益を享受できる活動(町内会活動や同窓会活動など)もできます。
よって、一般社団法人の活動できる範囲は大きいです。
2.利益を給与やボーナスに充てることができる
一般社団法人やNPO法人の話で、よく「非営利」という言葉が出てきます。
「非営利」という意味を多くの方が誤解されています。
多くの方は2つの点で誤解されています。
① 利益を出してはいけない
② 給与や報酬をもらってはいけない
(無料もしくは格安でサービスを提供しなければならない。)
これらはすべて誤った考え方です。ひとつずつ見ていきましょう。
まず、「非営利=利益を出してはいけない」ということではありません。
ここでいう「非営利」とは、事業で利益を出してはいけないということではなく、事業で利益を出してもかまわないが、「分配してはいけない」ということなのです。
株式会社の仕組みと比較すると分かりやすいかと思います。
株式会社の場合は、売上から経費(給与等人件費も経費です)を差し引いて利益が出ると、それを出資者(株主)に配当という形で分配することができます。
つまり会社が儲かれば利益が配当されるので株主は、儲けることができるのです。
これを法律上では「営利」と呼びます。
「非営利」法人であるということは、売上から経費(給与等人件費も経費です)を差し引いて利益が出ても、
出資者(正会員等)や寄付をして下さった方に分配することができません。
つまり配当金を出すことができないのです。
利益として余ったお金は、翌年度の活動のために繰越します。
「利益が出たら会員に還元するのではなく、次年度以降にさらに活動を大きくする為に使いましょう。」ということなのです。
二つ目は、「非営利」ということから、給与や報酬についても誤解されがちです。
非営利法人で働くことにはボランティア活動のイメージがあり、給与や報酬がもらえないと思われるかもしれません。
しかしもちろん、労働に見合った給料をもらうことはできますし、あらかじめ「賞与規定」を設けていれば、一般企業と同じようにボーナスをもらうことができます。
役員総数の3分の1の役員しかもらうことができませんが、「役員報酬」をもらうこともできます。
事業を続け、社会に貢献し続けるためにも、きちんと利益を上げる必要があるのです。
3.株式会社より設立費用が安い
株式会社の場合設立にかかる費用は約24万円であるのに対し、一般社団法人の場合約11万円で設立できます。
費用の内訳としては、定款認証に約5万円、登録免許税として6万円です。
ただし、これは全て自力で設立した場合の費用です。
法人設立を外部に依頼すれば、その分費用がかかります。
4.設立時や設立後に監督官庁の許認可が不要
NPO法人の場合は「都道府県庁又は内閣府」が所轄庁となり、NPO法人を監督する権限を有しますので、毎年度、収支報告書などの事業報告書類の提出が義務づけられています。
また、定款変更や役員の変更など登記記載事項が変更する度に所轄庁に変更報告書類を提出しなければいけません。
これらを面倒に感じられる方も多いです。
ところが、一般社団法人には「所轄庁」が存在しませんので、NPO法人のように事業報告書類や変更報告書類を提出する必要がありません。
「報告書の作成」という義務から開放される分、一般社団法人の方が運営しやすい法人ともいえます。
5.入会制限を設けることができる
NPO法人の場合は、設立趣旨や活動目的に賛同する個人・法人等の入会を妨げることはできません。
「この人と考えが合わない」
「何となく入会してほしくない」
といった理由で入会を拒むことができないということです。
一般社団法人の場合は、そのような規定がないため、
「○○の資格を有する者」「代表理事の許可が必要」というような入会制限を設けることができます。
自分の信頼できる人しか議決権を持って欲しくない・議決権を持つ人を選びたいというときは、一般社団法人を選んでください。
6.2人から設立できる
NPO法人の場合、最低10人そろえなければ設立できません。
一般社団法人でしたら、最低2人からスタートできます。
内訳としては社員2人以上、役員(理事)が1名以上で、社員が理事を兼任することができます。
通常「社員」という言葉は、「会社で働く人」という意味で使われていると思います。
一般社団法人の中で使われる「社員」という言葉は、「社員総会の議決権を持つ人」といった意味で使われます。
株式会社に当てはめると「株主」の立ち位置に近いと思います。
7.事務所の所在地を自宅やバーチャルオフィスにしてもよい
一般社団法人の登記上の事務所の所在地に関してはよくご質問を頂きます。
まず、自宅でもOKかという点でいうと、登記上は全く問題ありません。
ただ、契約上で登記NGの物件などもあったりするので、
賃貸の方やマンションの方などはその点で注意する必要があります。
次に株式会社の経営者の方などから多い質問ですが、
今の会社の登記している住所に一般社団法人の登記をしてもいいのかという質問です。
これも結論から言いますと問題ありません。
バーチャルオフィスなどは同じ住所にいくつもの登記が存在しています。
最後に、バーチャルオフィスでも大丈夫か?という点ですが、これも登記上はOKです。
ただ、銀行口座の開設が難しい場合があります。
住所だけ貸しているようなところでは、なかなか銀行口座が開設出来ず、住所を変更された方もいらっしゃいます。
また、郵便物が届かないという実務上の不便が生じることもあります。
私が運営をサポートしている起業支援センターでは、
横浜市青葉区で住所貸しの事業をしていますが、目の前に信用金庫さんがありまして、そこと話をして銀行口座の開設をお願いしています。
そんな感じで銀行と連携を取っているところもあるので、一概に言えませんが、銀行口座が開設出来ないのは結構痛いので、バーチャルオフィスの場合はそのあたりも事前に確認しておきましょう。
8.個人事業や任意団体より、法人格としての信用がつく
「営業先で法人化しているかどうか聞かれた」
「取引相手から法人化してくださいと言われた」
私のところに相談に来られる方で、このようにおっしゃる方がいらっしゃいます。
個人を相手にするビジネスでは法人化しているかどうかが問われることはあまりないかもしれませんが、法人が相手の場合、そのような信用度が重要になることもあります。
一般社団法人として法人化すれば、法人名義で銀行講座を開設したり、不動産の登記名義人になったりすることができます。
ただし、必ずしも法人化すればいいとは私は思いません。
というのも、法人化すれば信用度は増加しますが、その分お金や手間がかかります。
法人化が優先事項でなければ、他にすべきことがあると思います。
個人事業としてでも十分にできるビジネスモデルはあります。
個人でやるか法人化するかという点は多くの方が迷われるポイントだと思いますが、あなたのビジネスモデルを今一度見直して、個人事業がいいのか法人化が必要なのか考えてみてください。
まだあなたのビジネスモデルが明確でない場合は、ビジネスモデルの構築が優先事項になるでしょう。
9.出資金が不要
一般社団法人を設立する場合に支出しなければならない出資金は0円でも大丈夫です。
これは設立時に必要な税金などの法定費用を除いたもので、NPO法人も同様に0円で設立できます。
「1円起業」などという言葉もある株式会社の場合は、資本金1円から設立できます。
10.基金制度
資本金がゼロ円でも設立できますが、運営や事業の継続にはお金が要りますので、活動のための資金を集める方法がこの基金制度です。
定款に基金制度を採用することを明記し、基金の募集要項や返済手続きなどを定款に追記することで、この制度を利用することができるようになります。
基金へ財産を拠出するのは、一般社団法人を構成する社員でも、社員以外の個人・法人でも構いません。
ただし、基金の拠出を受けた一般社団法人は解散時に返済義務があります。
基金制度を利用して集めた財産が法人の財産となるわけではないことに注意してください。
一般社団法人の基金制度を利用して集めた財産は、資本金の一種というよりも「債務」として考えられます。
一般社団法人設立のデメリット
1.知名度の低さ
冒頭に書きましたが、一般社団法人は2008年にできた法律に基づいてできた法人です。
NPO法人に比べて設立が簡単で、事業内容の制約も少ないですが、その分知名度が低かったり、「一般社団法人とは何か?」というのが浸透していなかったりします。
公益性の高い事業をする場合、NPO法人の方が馴染みやすいと感じる方が多いような気がします。
ですが、近年は少しずつ一般社団法人の知名度も上がってきて、数も増えてきておりますので、これからも少しずつ知名度が上がっていくと思います。
「東京商工リサーチ」によると、2016年に新設された12万7,829社の法人のうち、一般社団法人は5,996社で、2008年度以来、毎年増加を続けているということです。
ちなみに、2015年度の法人の新設数は5,552社で、前年比で444社新設数が増加しており、新たに会社を起こす方も増えてきているようです。
2.剰余金の分配ができない
これはメリットの面でお話ししましたが、利益を出しても社員に分配することができません。
定款にその旨を定めても無効です。
利益配分をする場合、株式会社などの法人形態を選択するとよいでしょう。
3.収益事業には法人税がかかる
一般社団法人を設立して行う事業のうち、規定の34種類の収益事業と呼ばれるものには、法人税がかかります。
公益目的の事業に分類される事業収益に対してのみ、税制上の優遇措置が受けられます。
一般社団法人を運営する際で、あなたの事業が34種類の収益事業に分類されるかどうか判断に迷う場合は、税理士さんに相談してみてもよいでしょう。
4.官公庁の認可がない
メリットとデメリットは表裏一体でもありますので、所轄庁の許認可を必要としないことがデメリットにもなり得ます。
特に日本では、官公庁のお墨付きを得ていることが信頼度の増加に役立つことが多いかと思います。
面倒な手続きが必要ない分、公の許認可を得ているNPO法人などと比べると社会的信用度が低いと見なされることもあります。
5.法人住民税の支払い
これは一般社団法人に限らず法人化するにあたってのデメリットですが、赤字であっても年間7万円の法人住民税を支払わなければなりません。
個人事業であればこの費用は発生しませんので、法人化するデメリットの一つです。
この他にも納税や登記など、公的な手続きが継続的に必要になることは、慣れれば難しいものではないかもしれませんが、法人化全般のデメリットでしょう。
一般社団法人やNPO法人の設立をお考えの方は、まずは、設立事前相談にお申し込みください。