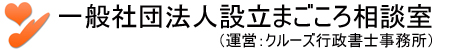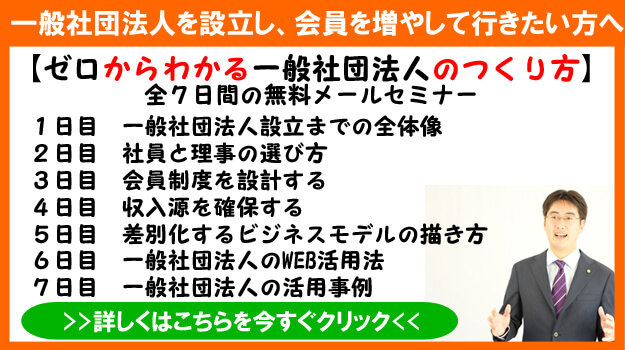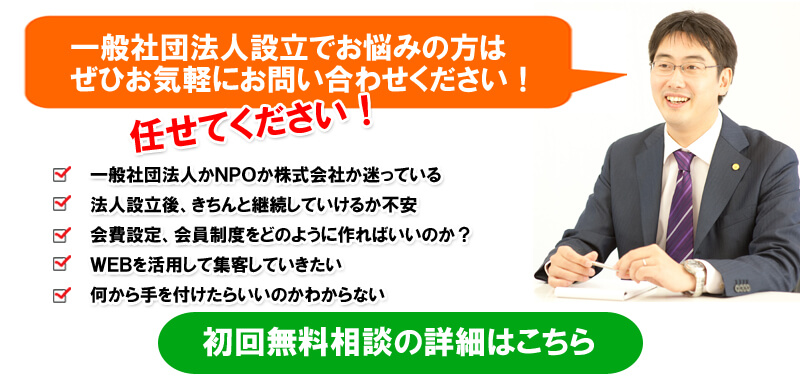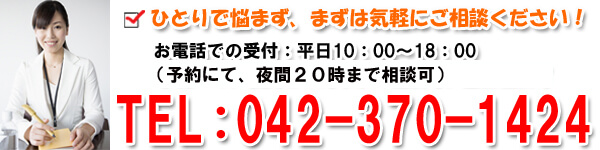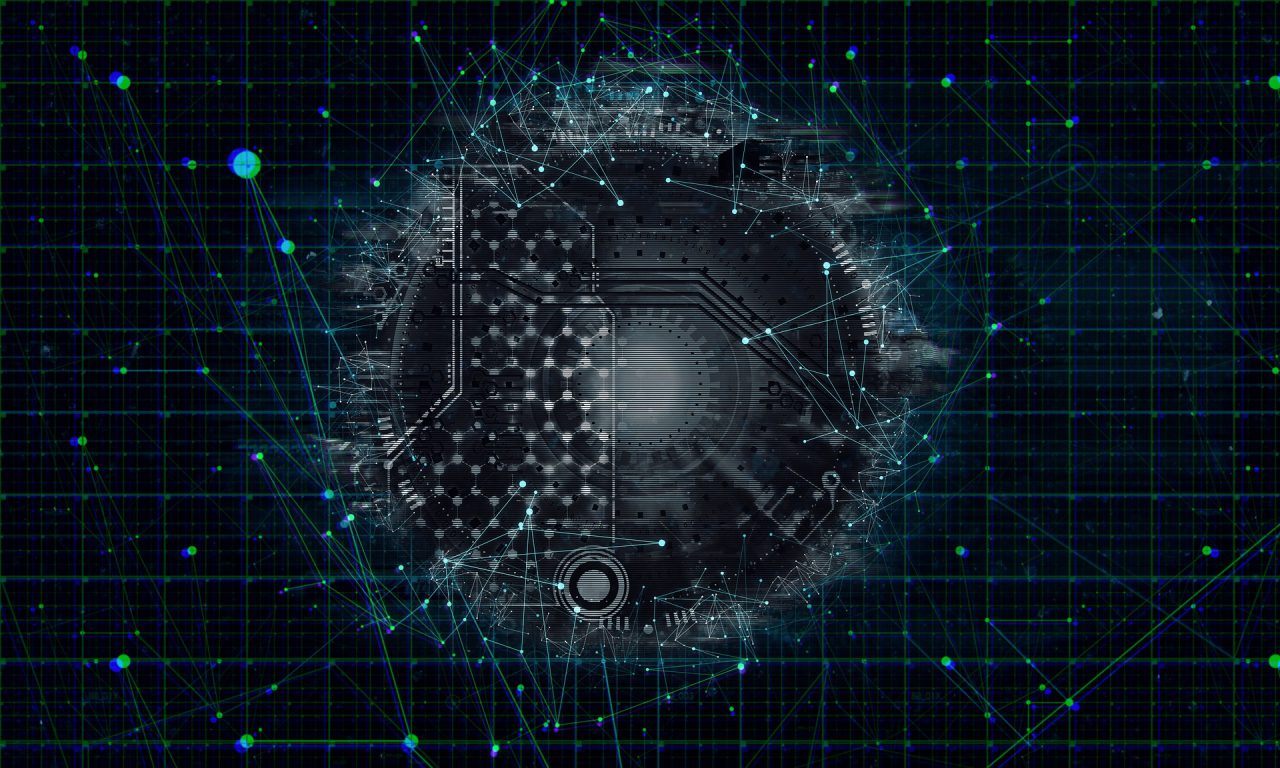一般社団法人の事業目的を作る上での注意事項
一般社団法人の定款を作成するにあたり、ひとつのポイントは事業目的の文言になります。
一般社団法人を設立するにあたって、事業目的は、定款の絶対的記載事項となっています。
定款の絶対的記載事項とは、定款に必ず書かなければならない内容、ということです。
ちなみに、一般社団法人を設立する際の絶対的記載事項としては、以下のようなものがあります。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立時社員の氏名又は名称及び住所
五 社員の資格の得喪に関する規定
六 公告方法
七 事業年度
さて、本題の事業目的の話に戻りますが、事業目的に書くべきこととは、この一般社団法人は何のために設立するか、一般社団法人を設立して何を事業として行うか、といったことです。
一般社団法人の事業目的を決める際の注意点としては、当然ながら法に反しないこと、そして公序良俗に反しないことが条件になります。
また、定款に目的を記載する際は、誰が見ても分かりやすいように書かなければなりません。
一般社団法人を設立する目的としては、例えば、
・資格の発行・認定
・異業種連携
・認知度アップ
・イベント・教室の開催
・研究機関
などが挙げられます。
よく、一般社団法人ではどういったことができて、どういったことができないのかということを聞かれます。
基本的には一般社団法人でできない事と言えば、剰余金の分配が出来ないという前提があるのですが、この事業はNGみたいなものはありません。
ただ、他の法律で制限されているものはできません。
例えば、大学を作るとかになりますが、学校法人ですし、病院を作るとかになると医療法人となります。
そう言った事業をすることはできませんので、要注意です。
当事務所のお客様で、最も多いのが資格の発行や講師の認定事業です。
私の感覚では全体の7割くらいの方が、このために一般社団法人を設立しています。
資格の発効とは、例えば、一般社団法人アロマ協会のような団体を立ち上げて、アロマに関する認定試験を開催したり、合格者に資格を付与したりします。
~検定などという民間資格をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、
そういった資格を発行しているのが、一般社団法人であることが多いです。
そして、冒頭で述べたように、定款にもこの事業目的を記載し、法務局に登記することになります。
一般社団法人をつくろうと思った目的はあるけど、
定款になんてどう書けばよいか分からない、という方もいらっしゃると思います。
定款には、事業内容を結構詳しく書く必要があります。
どう書けば全くわからない、という方は、まずはHPで既に設立されている一般社団法人の定款を参考にしてみてもよいでしょう。
他の一般社団法人と目的が完全に一緒ということはあまりないと思うので、完全に真似するなんてことにもならないでしょう。
ちなみに、「~協会」と名乗っている=一般社団法人というわけではありません。
必ずしも法人化していなくとも、「~協会」とは名乗れます。
法人化していないこのような団体を、任意団体といいます。
任意団体であっても、お金を集めてもよいのです。
大学のサークルがサークル費を取ったり、個人で経営しているピアノ教室が月謝を取るのと同じようなものです。
他のページでもお話ししましたが、一般社団法人であることによって、その資格の社会的信頼の増加や、知名度アップが期待できるのです。
特に、経営者のことを全く知らないお客様からすると、法人の方が安心できるという人も多いでしょう。
異業種連携とは、例えば、一般社団法人相続協会のようなものを設立し、
司法書士や弁護士、税理士、葬儀会社などが連携して、ワンストップでお客様の課題を解決する組織を作ったりしています。
セミナーや無料相談会を開催することで、認知度を上げたり、課題を抱えている人の役に立ちつつ、本業の仕事にもつなげていくようなビジネスモデルです。
こちらも、法人化した一般社団法人の主催として開催することで、顧客からの信頼度をアップさせることができるでしょう。
また、研究機関を目的としてつくられることもあります。
そして、目的を記載した後に、目的を達成するために以下の事業を行うと言ったような、行おうとしている事業について記載をします。
例えば、イベントの開催事業であったり、資格認定事業であったり、飲食店を行おうと考えているのであれば、飲食店の経営であったり、そういった文言を記載します。
注意すべき点としては、その事業をやるために、行政の許認可が必要な場合です。
例えば、介護保険事業を行う場合、介護保険事業の許可が必要ですが、その際に定款に記載する文言が決まっているのです。
もし、そういった許可が必要なものがあれば、事前に調べておくようにしましょう。
今まで、当事務所のお客様で、一般社団法人の設立に際して、許認可に関わるところでは、
障害者介護事業
高齢者介護事業
飲食店
古物商
くらいでした。
こちらも皆様が行いたい事業によって変わってくるので、注意してみてください。
よくある質問として、定款に記載した事項について必ずやらないといけないのかです。
一般社団法人の場合は、将来行う予定のあるものであれば、今すぐ事業化しなくても記載することは可能です。
この点は株式会社とは変わりません。
この部分を一度決めてから修正することは可能ですが、その場合は登録免許税が必要となります。
NPO法人の場合は、事業計画の提出が2年分必要で、その中で行う予定の物が記載されることになります。
ここ2年では事業化する予定がないが、10年後にやりたいことは記載することが出来ません。
このあたりが、一般社団法人とNPO法人の事業目的や事業内容の違いとなります。
まとめとして、一般社団法人を設立する時に事業目的や事業内容を考えるときは、将来事業化しそうなことも記載しておくのがいいかと思います。
ただ、あまりその数が多すぎると何の一般社団法人かがよくわからなくなるので、その点だけはご注意ください。