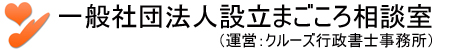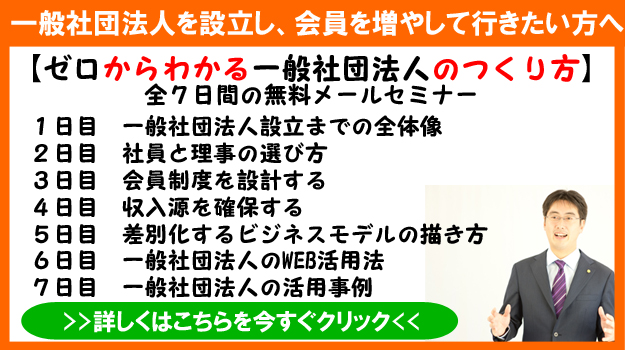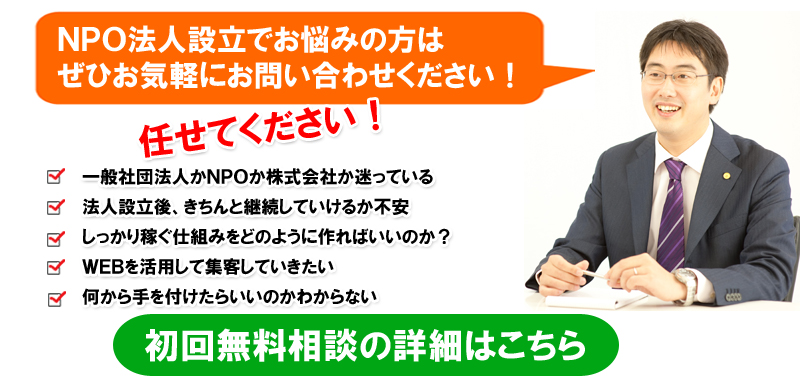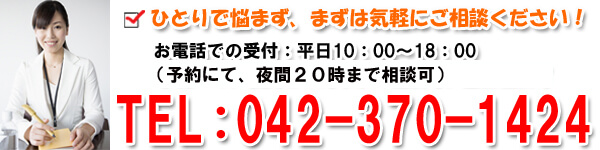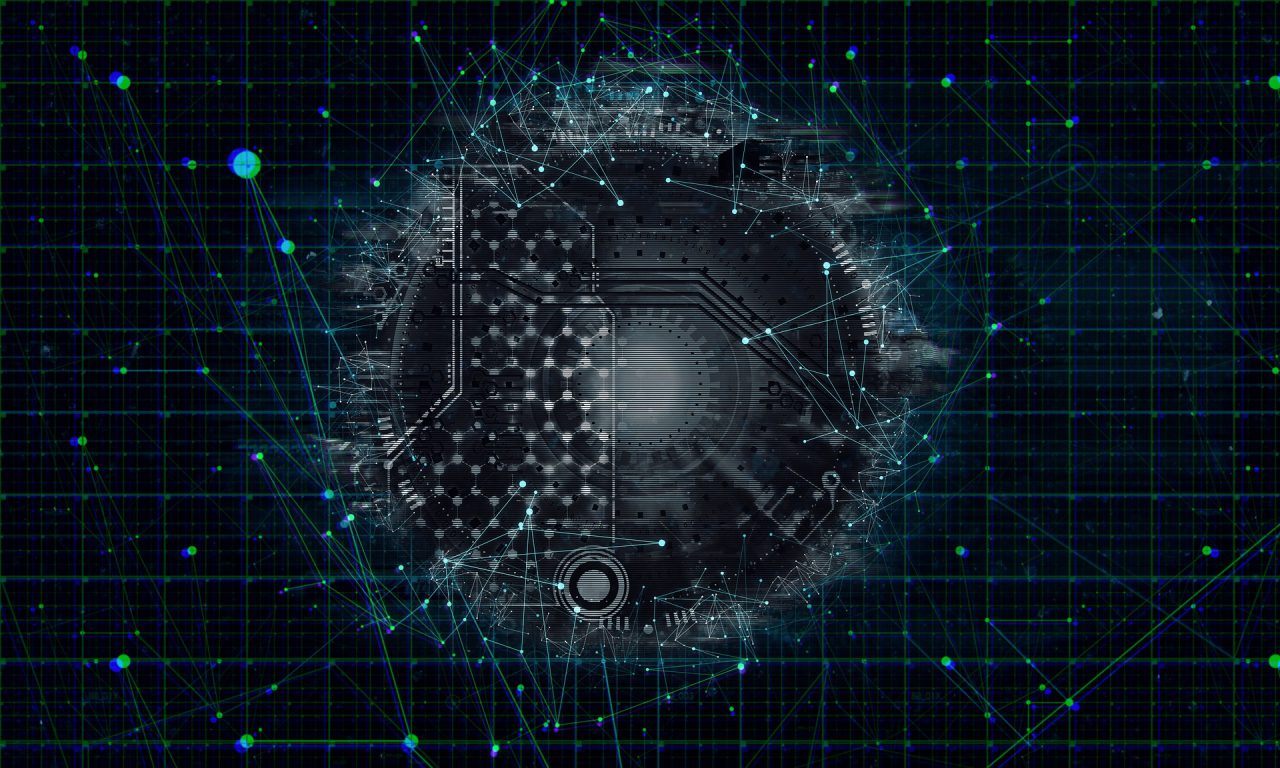NPO法人の設立要件は、主に以下のようなものが挙げられます。
1.主たる活動の目的が20分野の非営利活動のいずれかに該当すること
2.活動の対象が不特定多数であること
3.営利を目的としない
4.主たる目的が宗教活動、政治活動でないこと
5.特定の団体や個人の利益を目的としてはいけない
6.暴力団やその関連団体でないこと
7.社員が10名以上いること
8.社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
9.役員として、理事三人以上及び監事一人以上必要
10.全ての役員が欠格事由にあたらないこと
11.役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下
以下詳しく見ていきましょう。
1.主たる活動の目的が20分野の非営利活動のいずれかに該当すること
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
2.活動の対象が不特定多数であること
条文には「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」とあります。
つまり、会員のみを対象とした活動など、限定した範囲でのサービス提供が認められていません。(ここが一般社団法人との大きな違いです)
チェックポイントとしては、
![[check]](https://web.archive.org/web/20140327095357im_/http://npo.crews-g.com/image/face/check.png) 誰でも会員となれるか
誰でも会員となれるか
![[check]](https://web.archive.org/web/20140327095357im_/http://npo.crews-g.com/image/face/check.png) サービスは一般に公開されているか
サービスは一般に公開されているか
が挙げられます。
3.営利を目的としない
「営利を目的としない団体」「非営利」という意味を多くの方が誤解されています。
ここでいう「営利」とは構成員への利益の分配を意味します。
言い換えると、NPOは利益分配しない組織(団体)のことです。(ここが株式会社との大きな違いです。)
多くの方は3つの点で誤解されています。
① 利益を出してはいけない
② 給与や報酬をもらってはいけない
③ 無料もしくは格安でサービスを提供しなければならない。
これらはすべて誤った考え方です。
ひとつずつ見ていきましょう。
まず、「利益を出してはいけない」ということではありません。
NPO法人でいう「非営利」とは、事業で利益を出してはいけないということではなく、事業で利益を出してもかまわないが、「分配してはいけない」ということなのです。
ちょっと難しくなりました。
株式会社の仕組みと比較した方が分かりやすいかと思います。
株式会社の場合は、売上から経費(給与等人件費も経費です)を差し引いて利益が出ると、それを出資者(株主)に配当という形で分配することができます。
つまり会社が儲かれば利益が配当されるので、株主は儲けることができるのです。
これを法律上では「営利」と呼びます。
NPO法人が「非営利」法人ということは、売上から経費(給与等人件費も経費です)を差し引いて利益が出ても、出資者(正会員等)や寄付をして下さった方に分配することができません。
つまり配当金を出すことができないのです。
二つ目は「非営利」ということから、給与や報酬についても誤解されがちです。
NPO法人はボランティア活動のイメージがあり、給与や報酬がもらえないと思われるかもしれません。
よくそういうご相談もいただきます。
しかしもちろん、労働の対価として給料をもらうことはできますし、ボーナスの規定を設けていれば、ボーナスももらうことができます。
また、役員総数の3分の1の役員しかもらうことができませんが、「役員報酬」をもらうことはできます。
3つ目は、無料もしくは格安でサービスを提供しなければいけない、という誤解です。
「非営利」という言葉は、「分配してはいけない」ということでしたね。
ですので、正当なサービスの対価を頂くことは問題ありません。
給与や報酬を払わなければ、活動を続けていく事はできません。
もう一度おさらいすると、「非営利」とは売上から給与や報酬をもらい、活動にかかった経費を差し引いて、最終的に残った利益を「分配」してはいけないということです。
4.主たる目的が宗教活動、政治活動でないこと
特定非営利活動促進法2条2項に以下のようなことが書かれています。
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ハ 特定の公職(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
特定非営利活動促進法3条3項には、
特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
ともあります。
5.特定の団体や個人の利益を目的としてはいけない
NPO法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはいけません。
6.暴力団やその関連団体でないこと
特定非営利活動促進法12条3項に以下の規定があります。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第二号 に規定する暴力団をいう。以下この号及び第四十七条第六号において同じ。)
ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
7.社員が10名以上いること
社員が10名以上いることが、NPO法人の設立要件です。
ここで、「社員」という言葉で誤解をされる方がいます。
一般的に「社員」というと、会社の従業員をイメージされる方が多いかもしれません。
しかし、ここでいう「社員」とは「総会で議決権を有する会員」のことをさします。
会社で言う「株主」の方が、イメージ的には近いかもしれません。
「正会員」という呼ばれ方をすることもあります。
職員や従業員のことではありません。
社員には、個人でも法人でもなることができ、国籍、住所地、親族等の制限はなく、社員は役員(理事・監事)を兼ねることができます。
8.社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
NPO法人は、社員の入会・退会は自由でなくてはなりません。
NPO法人の理念に賛同する個人・法人等の入会を妨げることはできません。
「この人嫌い」「高齢だから」といった理由で入会を拒むことができないということです。
また、退会についても自由が認められています。
9.役員として、理事三人以上及び監事一人以上必要
NPO法人の役員として、理事三人以上及び監事一人以上が必要です。
理事とは、NPO法人の経営者(株式会社の取締役のようなもの)です。
監事とは、NPO法人の決算の監査、理事の法人運営が法令等に反していないか監視する役割があり、株式会社の監査役のようなものです。
役員になるには、欠格事由に該当しないことや、親族規定等もあり、どういった人がなれるのか要注意です。
10.役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下
「役員報酬」とは、役員としての報酬です。
役員とは理事と監事のことをいいます。
役員になると、3分の1以下の人しかお金をもらえないのではなく、役員が法人の職員を兼務している場合は、その労働の対価として「給与」をもらえます。
「給与」と「役員報酬」両方をもらうことも可能です。
以上、大まかな設立要件について説明してきました。
細かい所ではこれ以外にもありますが、まずはこの10項目をチェックしてみてください。
NPO法人は、株式会社や一般社団法人など他の法人に比べて要件が厳しく、設立要件をチェックしていくだけでも非常に手間と時間がかかります。
法律の条文を見ながら「私の活動は法律の要件を満たしているのか?」と確認していくと
「本当にいいのかな?」
と感じる人もいらっしゃるかもしれません。
はじめての人が要件を確認しながら書類を作成するのは、非常に大変なことと思います。
あなたの目的は「NPO法人の設立」ではありません。
「社会貢献活動を行うこと」「社会変革活動を行うこと」が目的であり本業だと思います。
立ち上げのため、ただえさえ時間がなくやることが盛りだくさんの時期に、NPO法人の申請手続きに時間をかけることが本当にいいことでしょうか?
NPO法人設立後も、様々な書類を提出しなければなりません。
まごころ相談室では、設立の手間を大幅に削減し、設立後の不安を解消できるよう、トータルでサポートをさせていただきます。
まずは、「私たちの活動はNPO法人として活動するのがいいのかな?」といったお悩みでも構いませんので、
お気軽にご相談いただければと思います。