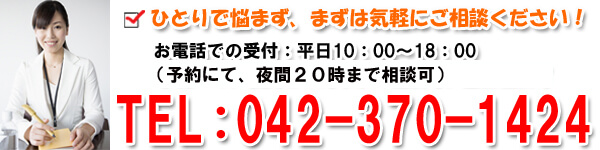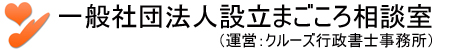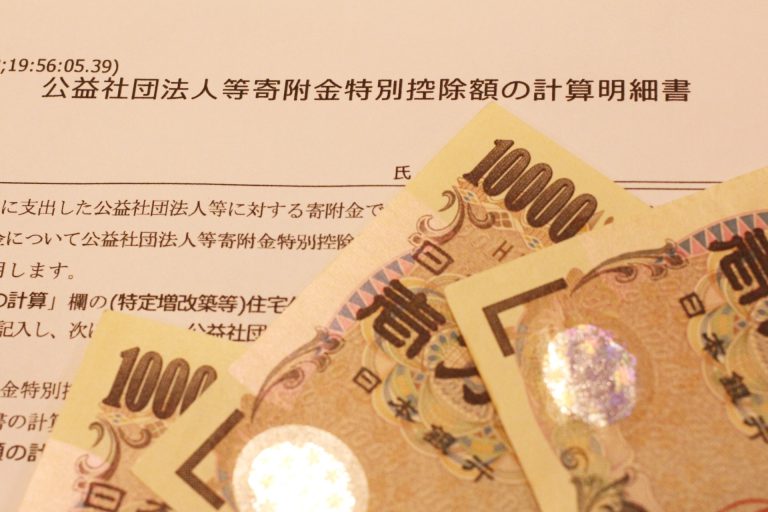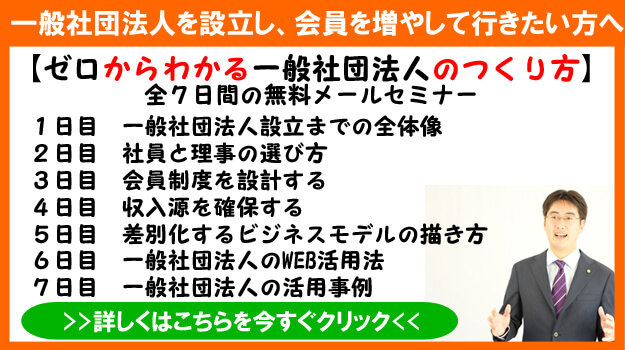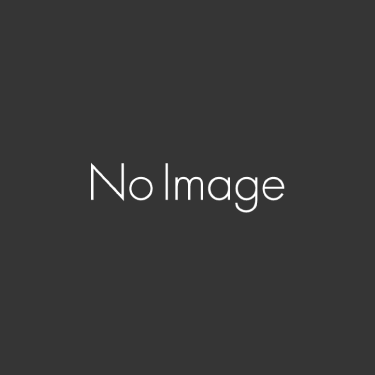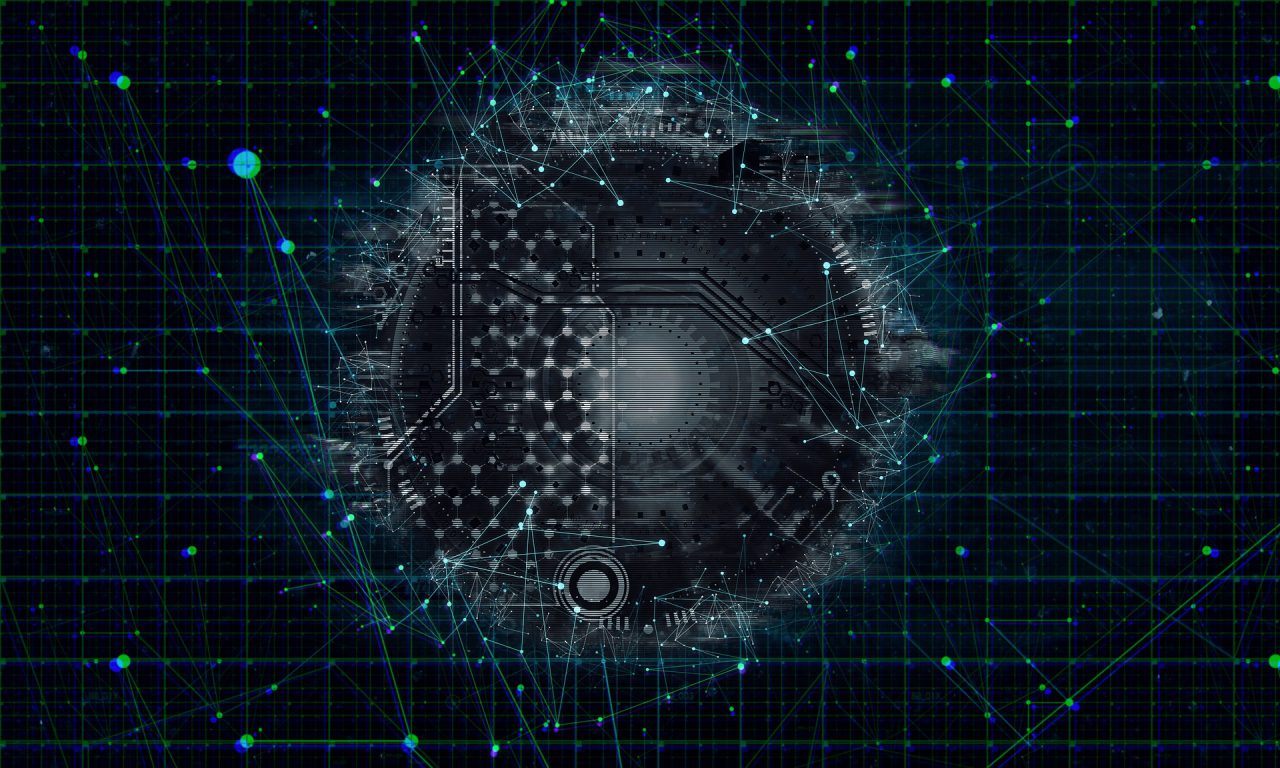1 一般社団法人と公益社団法人との違い
一般社団法人が内閣総理大臣または都道府県知事に申請をして、公益認定を受けたものが、公益社団法人です。
大きな違いは、一般社団法人が自由に事業目的を設定できる方法、公益社団法人は社会へより貢献することを一番の目的としなければいけないことです。
公益社団法人には、一般社団法人と比べて社会的信用の高さや税制の優遇などのメリットがありますが、そのぶん厳しい審査があります。
メリットについても含めて、詳しくご説明していきます。
2 公益認定基準について
一般社団法人が公益社団法人になるには、以下の18項目をすべて満たしている必要があります。
①公益目的事業を行うことを主たる目的とすること
②必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること
③この法人の関係者による特別の利益を与えないこと
④営利事業を営む者又は特定の個人や団体の利益を請願活動を行うものとして寄附など特別の利益を与える行為を行わないこと
⑤ 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものや公の位階エジプト善良の風俗を害する危険のある事業を行わないこと
⑥ 収入が実施費用を超えないと
見合わないこと⑦ 公目的益事業以外の事業を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業に支障を及ぼすおそれがないこと
⑧ 公益事業比率が百分の十以上となる協定であること
⑨ 遊休財産額が一定額を超えない協定であること
⑩ 理事と監事はそれぞれ三親等内の親族の合計数が投入の三分の一を超えないこと
⑪ 他の同一の団体の理事と監事はそれぞれ合計数が投入の三分の一を超えないものであること
⑫ 会計監査人を棄却すること
⑬ 理事、監事評及び議員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給の基準を定めていること
⑭ 一般社団法人にあっては、イロハ全て該当すること
イ 社員の資格は不当に差別的な取扱いや条件でないこと
ロ 社員総会の議決権に関する定めは、(1)と(2)のように定款に記載する(1)不当に差別的な取扱いをしないこと。 2)社員がこの法人に対して提供した金額で異なる取扱いを行わないこと
ハ理事会を置いていること
⑮ 他の団体の意思決定に支払うことができる株式その他の財産を保有していないこと
⑯ 公益目的事業を行うために究極な特定の財産について、必要な事項を定款で定めていること
⑰ 公益認定の取消しまたは合併により法人が消滅する場合、公益目的財産取得残額があるときは、これに相当する額の財産を平坦化の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨を定款で定めていること
⑱ 清算をする場合は残余財産を比例の事業を目的とする他の公益法人等に帰属させる旨を定款に定めていること
3 公益目的事業について
公益認定基準の一つ目「公益目的事業を行うことを主たる目的とすること」ですが、この「公益目的事業」は以下の「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」で定められていますしている23事業になります。
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 公衆衛生の向上を目的とする事業
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵かん養することを目的とする事業
十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
4 必要な最低人数のちがい
公益社団法人は、一般社団法人より必要人数が多くなります。
一般社団法人は最低2名で設立可能ですが、公益社団法人では
社員が2名
理事会を必ず設置し、理事が3名
監事1名
社員と理事は兼ねることはできますので、最低4名必要です。
一般社団法人から公益社団法人への転換をお考えでしたら、日々の運営の中で信頼できる人物を増やしておくことが大事と言えます。
5 申請について
内閣総理大臣(公益認定等委員会)または都道府県知事(合議制の機関)に申請書を提出します。
同時に定款や事業計画書なども必要です。
審査はもちろん「事業の公益性」がポイントになります。
審査期間は通常4カ月と言われていますが、修正などを求められることがありますので、余裕をもってスケジュールを組んでおいた方が良いでしょう。
6 費用について
申請時の費用は必要ありません。
法人名称を「一般社団法人」から「公益社団法人」に変更する手続きが必要ですが、これは法務局で変更登記となります。
登記に必要な登録免許税も非課税となりますので、こちらも必要ありません。
7 公益社団法人のメリット
7-1 社会的信用
公益社団法人の一番のメリットは、「社会的信用」でしょう。
必要書類を作成し法務局で登記をすれば設立できる一般社団法人と違い、公益社団法人は内閣総理大臣(公益認定等委員会)または都道府県知事(合議制の機関)の審査が必要です。
そのため、「国から認められた」団体として社会的信用度が高くなります。
この「社会的信用」は、寄付金を集める際に有利になります。
寄付する側の立場から考えると、貢献したい分野の中でもより信頼度が高い団体に寄付したいと思うでしょう。
また、税金の面でも有利なポイントがあります。
7-2 寄付金控除
これは、寄付金が特定寄附金(公益事業を行う法人や団体に対する寄附金)として認められると、その金額に応じて所得から一定金額が控除される制度です。
つまり、寄付をすることで税金が減らせることになるため、一般社団法人より寄付金が集めやすくなります。
7-3 みなし寄付金
収益事業から公益事業へ資金を移動させた場合、「寄付金」とみなして計算することができる制度です。
公益事業の赤字補てんできる額まで認められるため、収益事業での課税所得を少なくすることができます。
7-4 税金の優遇
公益事業での収益は非課税です。
一般社団法人では収益事業として課税されていた事業でも、公益事業と認定されると非課税になります。
また、一定の源泉所得税・消費税も非課税となるため、公益社団法人は法人税がかかりにくくなります。
このように、一般社団法人よりも厳しい審査を通ってきたからこそのメリットが、公益社団法人にはあります。
8 公益社団法人のデメリット
一般社団法人から公益社団法人に変わると、社会的信用が上がり、寄付金が集めやすく、税金の優遇があります。
しかし、事業活動に制限ができたり、運営していく上で負担が増えるのも事実です。
8-1 事業活動に制限ができる
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」で定められている23事業で活動しなければいけないのはもちろんですが、「公益目的事業比率が百分の五十以上となる見込みであること」などの「公益認定基準」があるため、一般社団法人に比べてかなり事業活動に制限ができます。
8-2 行政庁への報告
行政庁へ事業計画等や財産目録などを提出する必要があるため、事務作業の負担が増えます。
また行政庁による立入検査もあり、状況によっては公益認定取消しということもあります。
一般社団法人は、これらの報告は必要ありません。
また、公益認定取り消しとなった場合は、1ヶ月以内に公益目的財産を取得し残額に相当する額の財産を、類似の事業を目的とする他の公益法人等に帰属させなければいけません。
8-3 会計処理の複雑化
公益社団法人は貸借対照表内訳表において、「3区分会計」(公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計)となります。
この3区分での資金の移動はできませんので、きっちり分けておく必要があります。
メリットも多いですが公益社団法人、一般社団法人のように自由な事業は認められず、行政庁への定期報告義務や立入検査など、運営する上での負担が大きくなります。
公益社団法人としての義務を怠ると、公益認定が取消される可能性もあります。
ご自身が向かう事業には、どちらが向いているのか?
メリットだけではなく、真っ直ぐに決めた上で、そのままの選択をしてください。
一般社団法人やNPO法人の設立をお考えの方は、まずは、設立事前相談にお申し込みください。