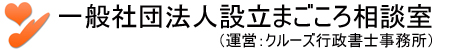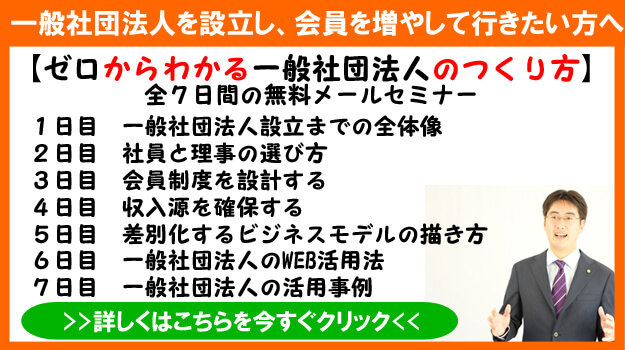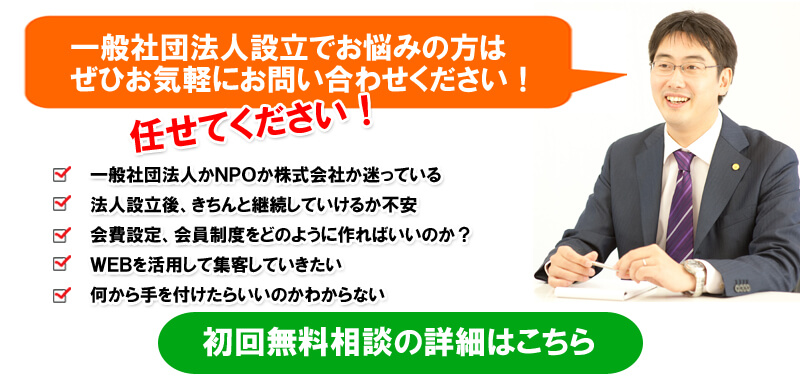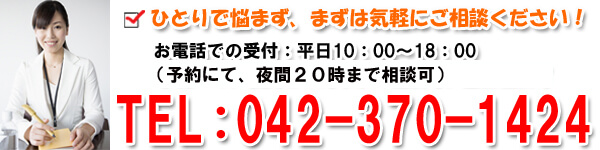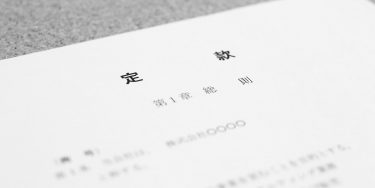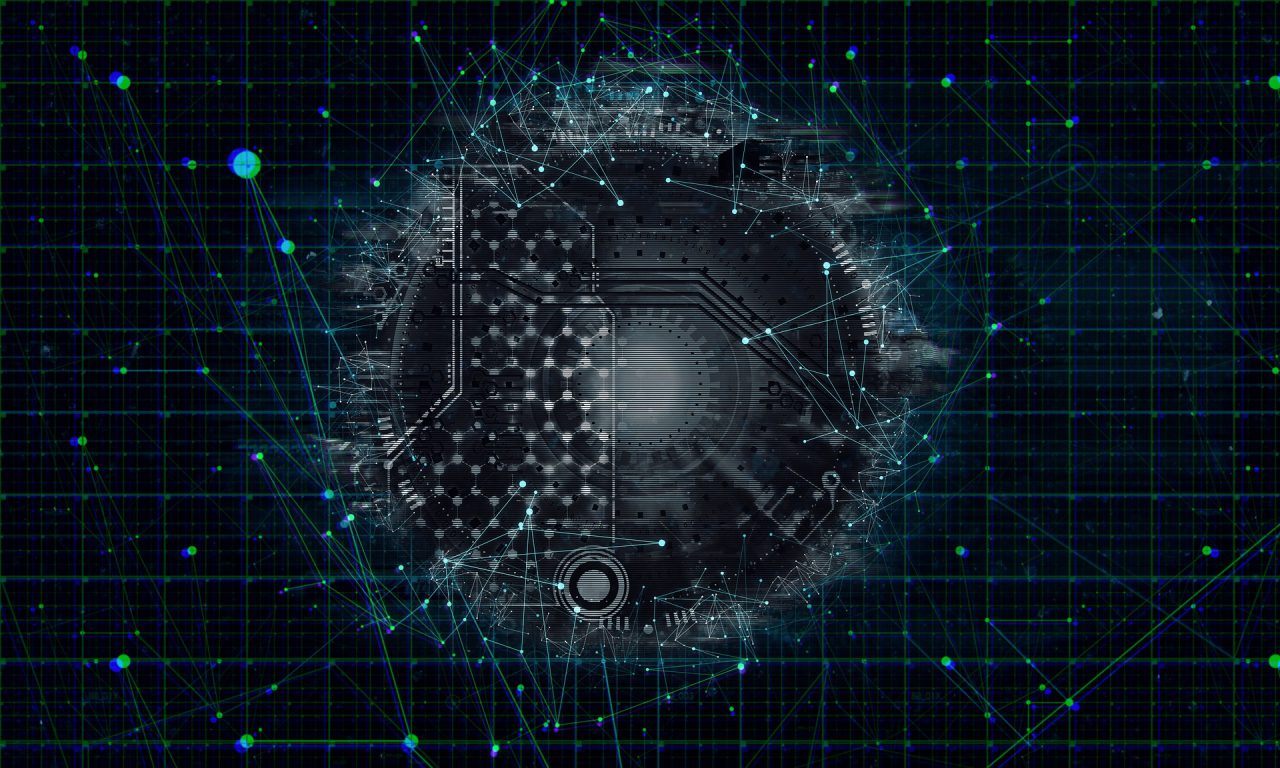一般社団法人の「定款」と「規約」の違い
「定款」と「規約」
どちらも一般社団法人を設立する際や運営していく際によく出てくる言葉ですが、「定款と規約の違いはなに?」と聞かれると、意外と答えるのが難かしいのではないでしょうか。
こちらのページでは、一般社団法人の定款と規約について簡単に説明したいと思います。
一般社団法人における定款
定款は一般社団法人を設立・運営するにあたって絶対になければならないものです。
一般社団法人をつくろうと思ったとき、手続き上まずやらなければならないことは、定款を作成し、それを公証人に認めてもらうことです。
ちなみに、定款には絶対的記載事項(必ず定款に書かなけらばならない内容)が、以下の7つと決められています。
一 、目的
二 、名称
三 、主たる事務所の所在地
四 、設立時社員の氏名又は名称及び住所
五 、社員の資格の得喪に関する規定
六 、公告方法
七 、事業年度
つまり、何という名前の一般社団法人を何のためにつくり、それを誰がどこで運営するのかといった基本的なことを定めるのが定款です。
これらのことがわからなければ法人として認証されようがありませんよね。
また、定款に定めても効力を発揮しない、つまり一般社団法人としてはやってはいけないことというのもあります。
それは
一、剰余金などの分配を受ける権利を与えるとの記載
二、法の定めにより社員総会の決議を必要とする事項に関して、社員総会以外の機関が決議できると定めた記載
三、社員総会で決議する事項の全てについて、社員が議決権を持たないとする記載
の三つです。
一つ目の、利益を配当に回してはいけないという決まりが、一般社団法人か非営利法人と呼ばれる根拠になっています。
この他にも、法の定めに反する内容は定款に書いても効果を発揮しません。
一般社団法人における規約
規約とは、一般社団法人とその会員との間のルールのようなものです。
ですので、定款で決められていることより細かい内容を決めることになります。
入会・脱退の方法や会費の集め方、活動上のルール、会員相互のルールなどを決めますが、規約の内容は定款の定めに反しないようにしなければなりません。
定款がその一般社団法人の決まりの中で一番最上位にあり、それに従属する形で規約が存在するようなイメージです。
規約は必ずつくらければならないわけではないので、設立の際などに無くても法的には問題ありません。
また、規約には必ずこれを書かなければならない、ということはありません。
しかし、トラブルを未然に防ぐ意味でも、ルールを明記して知っておいてもらうことは大切だと思います。
いざ定款や規約をつくろうと思っても、どのように書けばよいか分からないこともあるかと思います。
そのようなときには、インターネットで「定款 雛型」とか、「規約 見本」などと検索すれば、サンプルが出てくるので、少し参考にしてみるのもいいかもしれません。
定款や規約をつくることは、あなたの一般社団法人を守り、円滑な運営をすることにつながります。